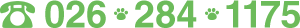重症熱性血小板減少症症候群(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome:SFTS)は、SFTSウイルスによって引き起こされる感染症です。主にマダニに咬まれて吸血されるときに感染し、犬猫だけでなく人にも感染する人と動物の共通感染症として注意が必要です。特に人と猫は重い症状がでるとされています。(猫の致死率は約60%と非常に高いです。)
静岡県獣医師会がわかりやすいリーフレットを作成してくれていますので、参考にしてください。
SFTSに感染すると、39-41℃の高熱、食欲不振、元気消失といった全身症状が現れます。消化器症状として嘔吐や下痢も頻繁に見られ、特徴的な症状として歯肉出血、鼻出血、血便などの出血傾向が認められます。また、黄疸や呼吸困難を呈する場合もあります。
血液検査では血小板数の減少が特徴的で、白血球数の減少や肝酵素値の上昇も同時に認められることが多く、これらの検査所見が診断の重要な手がかりとなります。
最も一般的な感染経路は、SFTSウイルスを保有するマダニに咬まれることです。また、感染した動物の血液や体液との直接接触による感染や、感染した小動物を捕食することによる経口感染も報告されています。特に外が大好きなワンちゃんや、外と中を行き来する猫では注意が必要です。
SFTSは人と動物の共通感染症であり、人への感染リスクも十分に考慮する必要があります。人も犬猫と同様にマダニ咬傷により感染する可能性があるほか、感染した犬猫の血液や体液に直接触れることで感染するリスクがあります。さらに、感染動物のくしゃみや咳による飛沫からの感染も報告されており、動物たちの感染時には十分な注意が必要です。
人がSFTSに感染すると、高熱、頭痛、筋肉痛といった全身症状に加え、嘔吐や下痢などの消化器症状、出血傾向が現れます。重症化すると多臓器不全を起こす可能性があり、場合によっては生命に関わる危険な状態となることもあります。最近は、マダニを介する人での感染症報告が相次いでニュース記事になっていますが、厚生労働省でも注意喚起を以前から行っています。ちなみに人のSFTSの致死率は日本で27%と報告されています。非常に致死率の高い疾患であるため、注意が必要です。
動物たちのSFTS感染予防には、マダニ予防薬の定期的な使用が最も効果的です。散歩時には草むらにはいるのを避けたいところですが、大好きで入ってしまう場合は帰宅後に丁寧なマダニチェックを行うことが重要です。また、野生動物のいるようなところを避けることで感染リスクを大幅に軽減できます。
飼い主様自身の予防対策として、野外活動時には長袖・長ズボンを着用し、虫除けスプレーを使用してマダニ咬傷を防ぐことが大切です。また、日頃から同居している動物たちの健康状態を注意深く観察し、体調不良の際には手袋を着用して看病し、手洗いを徹底してください。
SFTSの診断は、血液検査による血小板数や白血球数の確認から始まります。確定診断にはPCR検査によるウイルス遺伝子の検出や抗体検査が必要となります。症状や血液検査の結果からSFTSが疑われる場合は、速やかに詳細な検査を行います。
現在、SFTSに対する特効薬は存在しないため、治療は対症療法が中心となります。輸液療法による全身状態の安定化、必要に応じた輸血、二次感染予防のための抗生物質投与、その他の支持療法を組み合わせて行います。早期発見・早期治療が予後の改善につながるため、症状に気づいたら素早い対応が重要です。
動物に急な発熱と食欲不振が見られた場合、歯肉出血や鼻血などの出血傾向が認められた場合、嘔吐・下痢が継続している場合、またはマダニの付着を発見した場合は、動物病院を受診してください。
受診時には症状がいつから始まったか、どのような症状があるかを詳しく教えてください。また、最近の散歩コースや野外活動の有無、マダニの発見や除去の経験、他の同居動物や家族の健康状態についても重要な情報となりますので、併せて伝えてください。
SFTSは犬猫と人の両方に深刻な影響を与える可能性のある感染症です。マダニ予防を徹底し、動物たちの体調変化に注意を払うことが最も重要な対策となります。この病気は人と動物の共通感染症であるため、動物の体調不良時は適切な防護措置を取り、ご自身の健康管理にもご注意ください。人での症状が疑われる場合は、医療機関を受診し、動物との接触歴をお伝えください。気になる症状がございましたら、早めにご相談ください。