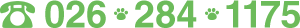近年、医療と同じように獣医療も日進月歩で進歩しており、高度で専門的な知識や技術を求められるシーンが増えてきています。
私たち小動物診療を生業とする獣医師は、基本的に全科診療を行っており、総合臨床医として日々動物たちの診療に臨んでいることがほとんどです。いわゆる「何かあったら真っ先に頼れる獣医さん」であり、そうあることを目指して、日々の診療をこなし、そして日々勉強しています。
ただ、私たち獣医師は、もちろん全てを知っていて全て治療できるわけではありません。それぞれの得意・不得意や、施設や医療機器などのハード面において、できることとできないことがあります。そうした中、多様なニーズに応えることができるよう、獣医師同士が連携して診断や治療に臨むことも一般的になってきました。
そこで今回は、当院からセカンドオピニオンをお願いする場合についてと、逆に当院へセカンドオピニオンを求めていらっしゃる場合について、簡単にお伝えしたいと思います。
先ずは、セカンドオピニオンとは何でしょうか。
セカンドオピニオンは、現在かかっている病気に対する診断や治療に関して、主治医以外の別の獣医師の第2の意見(セカンドオピニオン)を聞くことで、診断の正確性や治療法の選択肢を確認したり拡げたりすることを目的に行われます。一般的には、患者(飼主)の希望や主治医の判断により、「主治医の紹介」で専門病院や他の獣医師に意見を求めます。
セカンドオピニオンに関しての詳しい説明は、国立がん研究センターのホームページや、東京都保健医療局のホームページがわかりやすいので参考にしてください。
さて、本題に戻ります。最初に、当院からセカンドオピニオンをお願いする場合についてです。
当院の判断で、専門病院や特定の診療科が得意な近隣の動物病院への受診が適切と考えられた場合にご提案し、当院からの紹介を行って他の医療機関を受診することになります。技術的に治療困難な病気やその病気の診断や治療のために専門的な知識や器材が必要な場合には、診療中にご提案することがあります。
次に当院へセカンドオピニオンを求めていらっしゃる場合です。
先ず、今かかっている主治医の診断や治療に関する意見(ファーストオピニオン)を、ぼんやりでもいいので、飼主様ご自身で理解されているかをご確認ください。セカンドオピニオンは、主治医と患者(飼主)、第2の獣医師の三者で成り立つため、ファーストオピニオンの理解がとても重要です。もし、まだご理解されていない場合は、主治医とじっくりご相談ください。コミュニケーションの不足が理解の妨げになっている場合は、しっかり話をすることで信頼関係が強固なものとなり、より良い方向に向かうと思います。その上で、当院の意見を参考にしたいという場合に、ご相談にいらしていただくと実りのある話ができると思います。
ちなみに、セカンドオピニオンを求めていらっしゃる場合は、午前中の診察受付時間にいらしてください。午後の診療時間にいらしていただいてもお話をゆっくり伺う時間がとれず、それこそコミュニケーションが不足してしまいます。
最後に、注意していただきたいことがあります。それは、セカンドオピニオンを求めるのではなく、ドクターショッピングをしていないか?ということです。ドクターショッピングは、複数の医療機関を訪れて同じ症状についての診察を受け、複数の獣医師から意見や薬をもらう行為をさします。この場合、セカンドオピニオンで重要とされるファーストオピニオンを提示する主治医との信頼関係は構築されていないように思います。獣医療の現場では、かかっていた獣医師の診断や治療方針に納得できない場合にドクターショッピングが行われる印象がありますが、その多くはコミュニケーション不足が原因になっているように思われます。従って、不要なドクターショッピングとならないために、主治医とのコミュニケーションを大切にしてください。
もちろん、私たち獣医師側にも説明の仕方の問題や疑問点を聞きにくい雰囲気をつくってしまっているといった問題点がある場合もありますので、そうした場合は、医療機関を変えることで納得がいくこともあります。その点では、ドクターショッピングにも理があるかもしれません。
当院では、動物・ご家族・獣医療スタッフの3者間のコミュニケーションを大切にすることで信頼関係を築く努力を重ねておりますが、何かお気づきの点がございましたら、お気軽にご指摘いただけると幸いです。