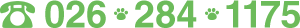先日長野県獣医師会員向けに、最近の獣医療現場で話題の「電気化学療法(ECT:ElectoroChemoTherapy)」に関する講演が開かれました。
獣医学領域では、分子標的薬以来の衝撃と言われている治療法です。
そこで、その治療法の概要を以下に記載しますので、参考にしていただければ幸いです。
ECTは、腫瘍(がん)に対する局所治療のひとつで、ヨーロッパでは1997年から小動物の治療に応用を開始している治療法です。組織に対して電圧をかけることのできる器械を用いて実施します。
あらかじめ、抗がん剤を全身または局所に投与します(全身投与と局所投与を同時に行うこともあります)。その後、腫瘍組織に対して電極を用いて電圧をかけます。腫瘍組織に電圧をかけると一過性に細胞膜の透過性が亢進し、腫瘍細胞内に抗がん剤が大量に入ることが可能になります。そうすると、腫瘍細胞内に大量の抗がん剤が一気に流れ込むので腫瘍細胞を死滅させることができるのです。
こうした直接作用の他にも、電圧をかけることで、腫瘍周辺の血管を障害することができたり(Vascular Lock)、ダメージを受けた腫瘍細胞から漏れ出た腫瘍関連抗原を免疫担当細胞が認知することによる腫瘍への免疫学的アタックができたりなど、他の効果も期待することができます。
もちろん、良い面ばかりではありません。腫瘍組織周囲の正常組織にも同様の効果が発現するため、腫瘍組織を含む周囲正常組織が腫れたり赤くなったり、痛みや熱感が出てきたり、または壊死脱落したりすることがあります。これをダウンタイムといいます。ヒトの美容外科領域ではよく使われる用語ですが、これは施術後に体が回復して通常の生活に戻れるまでの期間を指し、ECTでは、腫瘍サイズが縮小し、周囲組織が回復してくることを指します。このダウンタイムを経て、腫瘍が退縮していきます。多くの組織では、正常細胞の方が腫瘍細胞よりダメージに強いのです。
様々な腫瘍に適応されるECTですが、特に、外科的な切除が難しい顔面の腫瘍、断脚術を要するような四肢の腫瘍、の治療の選択肢として提示できる場合が多いとされています。
こうして色々述べておきながら、当院では器械も経験もないため、ECTを実施することができません。
幸い、長野市内で実施可能な施設(当院院長の大学の先輩の動物病院です)がありますし、少し遠いですが、埼玉の日本小動物がんセンターでは放射線治療などの他の治療選択肢を含めて検討・実施可能です。
こうした治療の選択肢が増えたことは非常に喜ばしい出来事であり、それを利用できる環境があります。ひとつの治療法として認識していただければ幸いです。