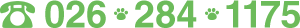私のような小動物臨床に関わる獣医師は、世界的に提唱されている「ワンヘルス」という概念のもと、日々の診療を通して動物たちの健康をサポートするとともに常に人の心身の健康に配慮することを心がけています。
そこで、最近の報告のうち、国立環境研究所の谷口氏による「伴侶動物との共生による健康効果」という論説が興味深かったため、ここに少し紹介させていただこうと思います。
日本は超高齢社会になり、2023年の高齢者割合は約29%と非常に高く、疾患の予防や管理に加えて、健康長寿の推進が喫緊の課題となっています。
健康長寿を実現するためには、「フレイル(虚弱)」を予防することが重要とされています。フレイルは「体の予備力が低下し、身体機能障害に陥りやすい状態」であり、フレイルに該当する高齢者は、要介護リスクが2倍以上高くなることが知られています。
そこで、伴侶動物(主に犬)との暮らしがフレイル発生に及ぼす影響について調査が実施されたところ、犬と暮していない人に比べて、犬と暮らしている人のフレイル発生リスクは、約20%も低いことが判明しました。
また、犬と一緒に暮らすことで死亡リスクが低下することも知られています。欧米の研究では、犬と暮らす人は、犬と暮らしていない人に比べて死亡リスクが24%低下することが明らかになっています。
日本でも同様の死亡リスクに関する調査が実施されていますが、日本ではさらに拡張した概念として、自立喪失(要介護発生または要介護発生前の死亡)のリスクが46%も低下したことが明らかになっています。
さらには、犬と暮らしている人は、犬と暮らしていない人に比べて、認知症発症リスクが40%低いことも明らかになっています。
ここまで犬との共生の話ですが、猫についても自立喪失リスクに関する調査が実施されており、猫と暮らしている人は、猫と暮らしていない人に比べて、自立喪失リスクが38%低下すると言われています。
その他の調査結果として、伴侶動物(犬や猫)と一緒に暮らすシニアは、そうでないシニアに比べて、月額介護費用が半額であることも示されています。
こうした事実を改めてみてみると、動物医療やそのほか動物関連業種に関わる私たちのような人間は大いに納得できるのではないでしょうか。確かに日々の仕事で接する方々は、明るく快活なのです。
それぞれ調査の考察によれば、特に犬との共生は、散歩などの規則正しい生活、身体活動量の増加、社会参加機会の増加などが期待され、それに応じて、各種リスクが低下することが述べられています。確かにそれらは、もっともな意見ですが、犬に限らず猫やウサギなどの動物たちも心の癒しや、日々の生活リズムの矯正に大いに貢献してくれていますので、伴侶動物全般に同様のことが言えるのではないでしょうか。
以前から、動物がいる生活の効用は広く謳われてきましたが、改めてこうした事実をもとにその効用を感じ直すことができるかもしれません。今後も、当院を含む各動物診療施設が、「ワンヘルス」を道しるべに人と動物がより良く生きていく、そんな社会への貢献ができるように日々を過ごしたいと思います。